 京都清水寺、243年ぶりの秘仏開帳が新潟で開催!?
京都清水寺、243年ぶりの秘仏開帳が新潟で開催!?
少し時間はさかのぼります。
とある猛暑の日。ネットでちらちらニュースを見ていたところ、とんでもないニュースが飛び込んできました。
「『京都 清水寺展』新潟万代島美術館開催。奥の院ご本尊も登場します。」(要約)
な、な、な、
なんですとーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!
清水寺奥ノ院のご本尊が出開帳(しゅつかいちょう)!!?
まじでですか!??
私は仕事部屋でひとり叫びました。あんまり驚いたので、FBでも書いてしまいました。この驚きをだれかと共有したい、そんな気持ちでいっぱい…。
なぜ私がこんなに驚いているのかというと、清水寺、というのは、皆さんもよくご存じのあの三年坂とかのある「清水寺」なのですが、清水寺には有名な秘仏が二躰いらっしゃいます。
そのうちの一躰、奥の院のご本尊が、こともあろうに「出開帳」なんて!!本当に信じられない事態です。
*出開帳というのは、お寺さん内でご開帳するのではなく、どこが他の土地に出張してご開帳する、ということです。
まずこの奥の院のご本尊は、平成15年に「243年」!ぶりにご開帳され、仏像ファンの間では、一大ニュースになりました。
243年ぶりですよ?!!
前にあけたときは、1762年ごろってことですよね。徳川将軍10代目家治の時ってことですよ。えらいこと昔です。
実は、清水寺は、火事の多いお寺さんなのです。創建されたのは778年(奈良時代)のことですが、そのあと何度も何度も火事で焼けては、再建されているお寺さんです。
江戸時代にも全焼してますが、三代将軍家光公によって再建され、現在に至っています。243年前になぜご開帳されたのかはわかりませんが、本堂のご本尊のほうは、運営資金を集める勧進のために、江戸時代には何度も江戸に出開帳していることを見ると、そういった何か経済的理由があったのかもしれません。
今回の出開帳も、家光公による「寛永の再建」から380年を数えたことを記念して、とのことなのですが、それにしても、どうして新潟で??!また、このあと沖縄県立博物館を巡回します。新潟と、沖縄……。
正直言って、相当に不思議なことです。何か深いご縁がある、ってことなんでしょうか。
すみません、前置きが長くなってしまいましたが、これはもう、前回2003年の時には、仕事で京都に行くのを断念した私としましては、神の恵み、いや観音さんの恵みってやつじゃないですか。どうにかこうにか見に行かないわけにはいかん!…とスケジュール表とにらめっこです。
ちょうど、ありをりあるが一周年を迎えるので、その記念にちょっと出張したいと思ってましたので、この新潟へ清水寺の観音さんに会いに行くというのを、ぶっこむことにしました。
調べてみますと、高速バスで行くとすごくお安い!ホテルも平日だと半額で泊まれる!
…こうして、一周年記念取材旅行は新潟に決定したのでした。
国内では15年ぶりの高速バスでのブツタビ
10月1日。いよいよ待ちに待った新潟ブツタビに出発です!
朝8時池袋発の長岡バスに乗って出発!
実は高速バス、国内ですと学生以来の体験です。しかも新潟は初めて。バスってなんかワクワクしますね。電車もいいけど、バスもまたいい。不思議な旅情があって!!
約5時間の旅です。

(写真:私が載った高速バス。途中PAにて)
時間があまりになかったので、新潟についてあまりよくわかっていない私は、バス内で一生懸命ガイドブックとにらめっこ。
一泊はするものの、時間はそんなにたくさんはありません。本当は新潟市内だけではなくて、村上市や長岡市やたくさん行ってみたいところはありましたが、現実を考えて、新潟市内だけにしぼりました。
新潟市内は、どちらかというと明治以降ハイカラな港町だった場所なので、古い仏像は見当たりません。そういう意味では、今回のブツタビはとにかくお目当ての『京都清水寺展』にしぼったほうがよさそうです。
後は市内を巡回しているバスに乗って、明治から昭和の名家のお庭など見ることにしよう、と決めました。こちらはどちらかというと「石部」の範疇……。
 (写真:途中のPAで見た信濃川。だんだん気持ちが上がってきましたよ!)
(写真:途中のPAで見た信濃川。だんだん気持ちが上がってきましたよ!)
それにしても、バスでの移動はとても楽しかった。景色もよく見えますし、また、バスの運転手さんもすごく親切なんですよね。
車内のパーソナルスペースもかなり広いですし。時間は新幹線よりかかっちゃいますけど、お値段3分の一くらいですから、この快適さも含め、本当にいいですね。
さて、そんなこんなで、予定より30分早く、新潟駅に着きました。時間はだいたい13時。
13時といえば、そうです。お昼ご飯食べないと!!
お昼ご飯は、お寿司お寿司お寿司!!!
新潟に行くと決めてから、到着して最初のごはんは「生もの」と決めてました。美味しい新潟の海産物をまずいただきたい!と。
ネットなどで情報収集してみると、意外とネガティブな情報も多く見受けられました。総合しますと、新潟市内(駅に近いエリア)ですと、お寿司は東京とそんなに変わらない…て感じの評価なんです。大きな都市ですから、しょうがないですよね。だけど、私はどうしても地の魚が食べたいのです!
そんなことで、またネットでいろいろ見ていると、私がこれから行こうとしている「万代島美術館」の近くに、評判の回転すし屋さん発見。佐渡の魚を食べさせてくれるというではありませんか!?
よし。ここだ!!
駅から歩いて20分ほどで到着しました。もうおなかはペコペコです。

やっと着いた~!「回転寿司 弁慶」です!
幸いなことに、13時半ぐらいで時間も外れていたからでしょうか、待たずにすぐ座れました。普段は大人気なので、けっこう並ぶらしいですよ。
メニューを見て「佐渡産」と書いてあるものを、全部頼もう、と意気込むワタクシ。
佐渡といえば、イカですよ。イカイカ。すみませーんイカくださーい。

見てください、このツヤを! アオリイカ最高~♪
佐渡。いいなあ、佐渡…。
実は、私にとって佐渡はとても懐かしい、大好きな場所なのです。
10年以上前の話ですが、仕事が大変すぎて壊れかけていた私と友人KとMは、このどうしようもない状況の打開策として、「これ以上ないってくらい落ちたら、もう上がるしかないってそう思うのはどうか」と思いいたりました。
その時、友人Mが、力強くつぶやきました。
「…流人だ。流人の気分を味わうべきだ」
日本史専攻の友人Mは、絶えず渋い打開策を提案してくれる力強き人物です。その時も、「流人」という力強いテーマを投げ込んでくれました。
なるほど、流人か…
それは、私とKにとって、思いもよらぬ投げかけでしたが、心境的にはばっちりはまりました。最初は隠岐の島が候補に挙がりましたが、さすがにちょっと遠すぎます。次に八丈島が上がりますが、南国な感じがして、なんかちょっと今回は違います。
そこで、残ったのが「佐渡」だったのです。
「行くぞ!佐渡に!!」
(←この辺りで、実はもうかなり復活していることに気付かない三人)
こうして訪れた佐渡は、「流人気分」なんてとんでもない。本当に素晴らしい場所でした。
宿も「一番人気がなさそうで、建物も崩れそうな、いけてなさそうな民宿」を、あえてセレクト。ところが、確かにその宿は建物はボロボロだったのですが、おかみさんはいい人だし、ご飯は美味しいし、海はきれいだしで「いけてない」どころか「いうことなし」だったんです。
そのお宿で食べた、イカの美味しかったこと!
夕ご飯はイカ尽くしって感じでしたけど、生で食べても焼いても煮ても、ま~間違いない旨さ。
どん底気分を味わうつもりだった三人でしたが、すっかり楽しくなってしまって、見事に復活を遂げたのでした。
………
……と(回想シーンが長すぎですけど)二貫のアオリイカをいただいた瞬間、この時の記憶が走馬灯のように駆け抜けました。
佐渡、今回はいけないけど、また行きたいな…。
(続く)

 いちばん左は多分イサキ、中央は今回最も高価だったノドグロ、左はブリです。
いちばん左は多分イサキ、中央は今回最も高価だったノドグロ、左はブリです。 こののっぽな建物が、万代島美術館の入っている「朱鷺メッセ」。弁慶の入っている「ピア万代」という建物から歩いて10分弱。こちらの5階に美術館が入っています。
こののっぽな建物が、万代島美術館の入っている「朱鷺メッセ」。弁慶の入っている「ピア万代」という建物から歩いて10分弱。こちらの5階に美術館が入っています。 朱鷺メッセに入って、美術館に行く前にちょっと寄り道。最上階にある展望台に行ってみました。手前に見えるちょっと黄色い青の流れが信濃川、その先にあるのが日本海です。この万代島というのは信濃川の河口にある中洲なんですね、たぶん。
朱鷺メッセに入って、美術館に行く前にちょっと寄り道。最上階にある展望台に行ってみました。手前に見えるちょっと黄色い青の流れが信濃川、その先にあるのが日本海です。この万代島というのは信濃川の河口にある中洲なんですね、たぶん。 案内板?発見。
案内板?発見。





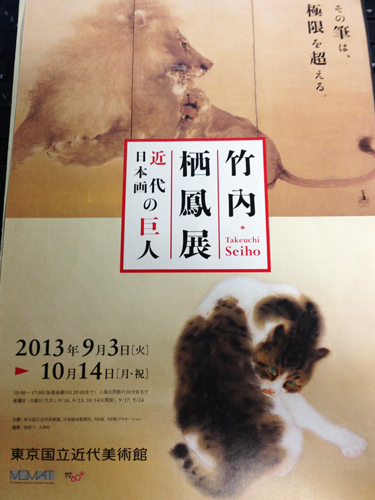




 そして、こちら。「庚申塔」です。庚申塔は道教由来の「庚申待ち」が基になってたてられているものです。『日本石造美術辞典』(川勝政太郎著)を見てみましょう。
そして、こちら。「庚申塔」です。庚申塔は道教由来の「庚申待ち」が基になってたてられているものです。『日本石造美術辞典』(川勝政太郎著)を見てみましょう。