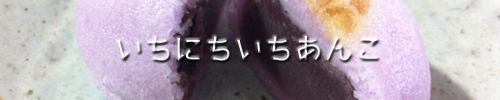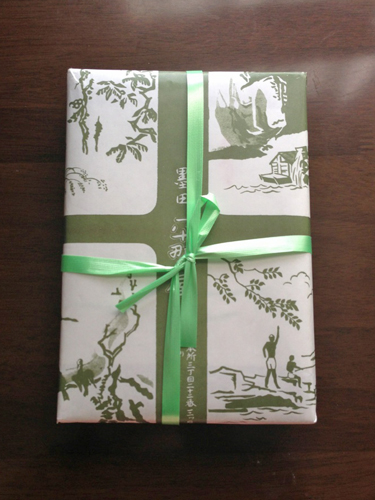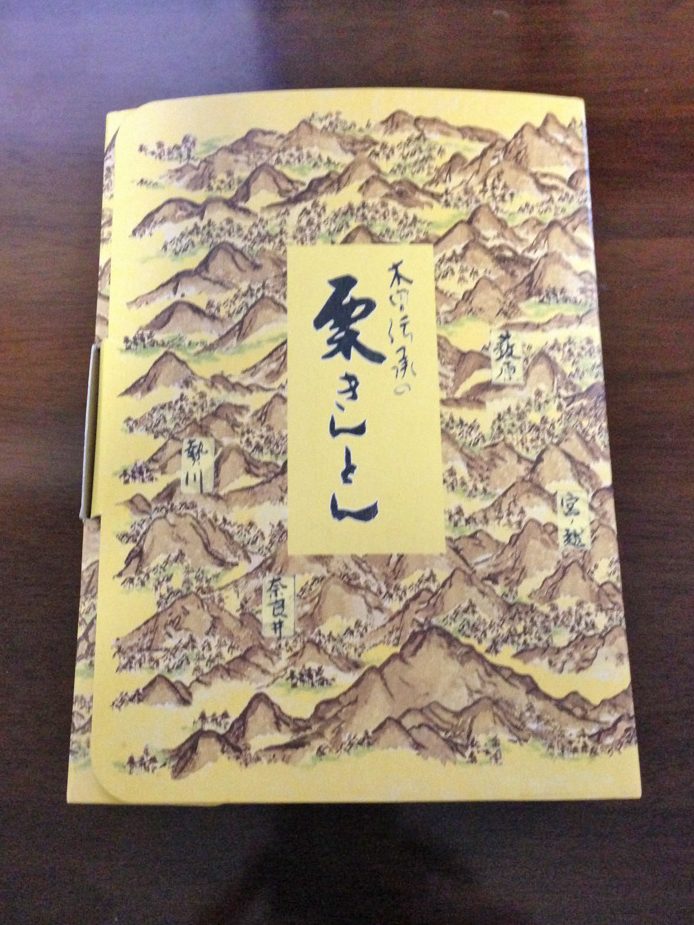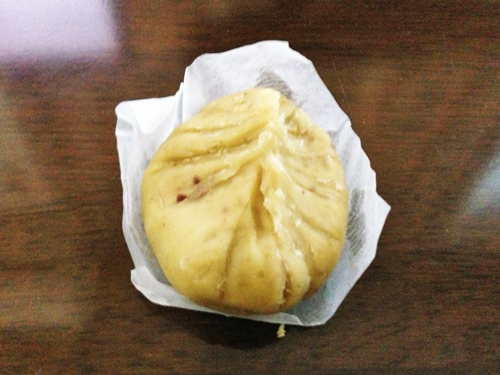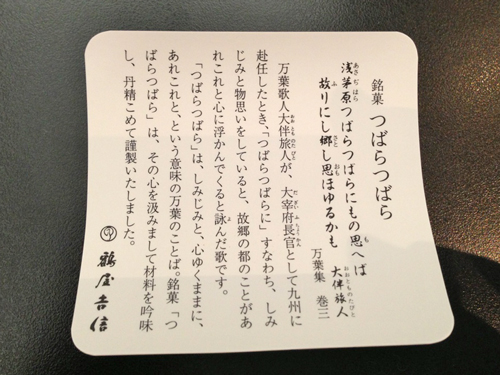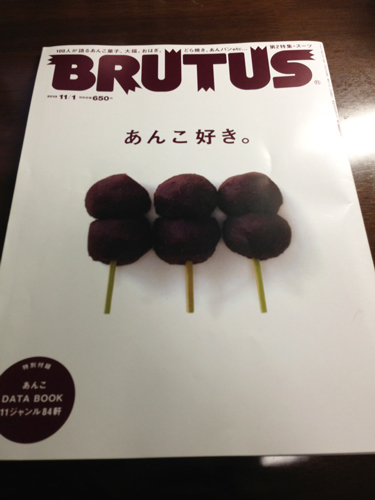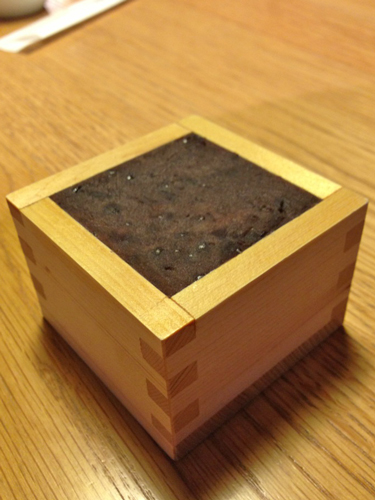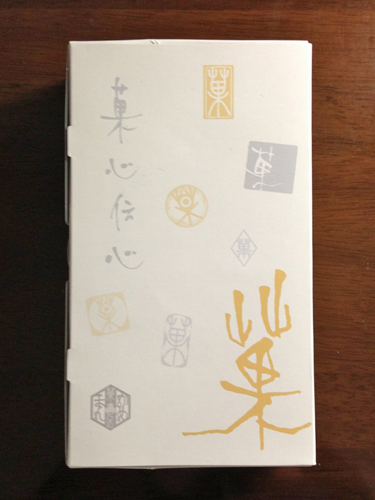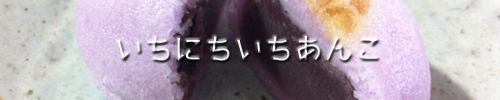 台風がどうにかそれてくれて、昨日は晴れ間も見えましたね。
台風がどうにかそれてくれて、昨日は晴れ間も見えましたね。
私は、昨日は100パーセント休日!という一日。午前中には新宿区が主催する「国際都市新宿 踊りの祭典2013」を見て、午後からは太田美術館で『笑いの浮世絵』展を堪能しました。
同行者は、いつものメンバー。
元同僚のS氏、ドキュメンタリー系TVディレクターのKさん、フリー編集者の先輩・Yさん。面白がりチーム集結!です。
『笑いの浮世絵』はまたあらためてご紹介したいと思いますが、今日はとにかくいちあんこ。
いつもおしゃれな情報に詳しいS氏とKさんが、夕ご飯にとおすすめカフェに連れて行ってくれました!渋谷ヒカリエにある「d47 食堂」さんです!
こちらは、「d design travel」という、新しいスタイルの旅行雑誌の編集部が提供する「食堂」。ヒカリエの8階にありますよ。
d design travelさんというのは
【「ロングライフデザインをテーマに活動する私たち D&DEPARTMENT PROJECT が、47都道府県それぞれにある、その土地に長く続く「個性」「らしさ」を、デザイン的観点から選びだして、観光ガイドとしてまとめたものが「d design travel」です。】(HPから抜粋)
という、なんだか素敵なムーブメントおこしつつあるデザイン集団さんのようです。
編集部セレクトの食堂のほかに、d47 museumというギャラリーも併設されてらっしゃるとのこと。
 今季のテーマは「富山県」なんだそうです。富山の名物が様々並んでいて、その一部は買うこともできます。
今季のテーマは「富山県」なんだそうです。富山の名物が様々並んでいて、その一部は買うこともできます。
このギャラリーと連動して、「食堂」のほうでも、限定の定食が「富山県」となってました。こんなかんじで食堂は、各都道府県の名物を食べさせてくれる、というわけなのです。
 定食は、各都道府県のものが毎月登場。10種類くらいの種類の中から、私が選んだのは「大分県」。大分の名物「りゅうきゅう」をメインとしてお定食です。
定食は、各都道府県のものが毎月登場。10種類くらいの種類の中から、私が選んだのは「大分県」。大分の名物「りゅうきゅう」をメインとしてお定食です。
「ぶりの刺身をタレに漬け込み薬味をのせた、郷土料理の「りゅうきゅう」。茄子とゴーヤを味噌で炒めた「おらんだ」と、クロメ豆腐の小鉢。」(HPより抜粋)
りゅうきゅうは、大分に行ったときにもいただいてとても美味しかったのですが、こちらのりゅうきゅうも負けず劣らず。ごはんも美味しいお米で、夢中になっていただいちゃいました。
さて、そして、ここで終わるわけにはいきません。
デザートです。そうです。「あんこ」でございます!
デザートメニューを見ると、「おはぎ」がありますよ。
でも、おなかがいっぱいなので、お萩はちょっと重い気がすると思って、思わず和栗のブラマンジュを頼んでしまいました(栗も大好き)。Yさんが頼んだおはぎを見ると…
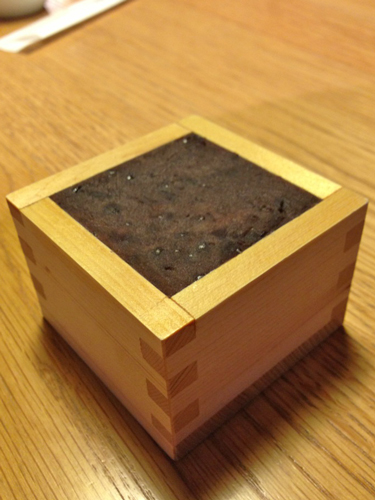 おおおお!これがおはぎ??
おおおお!これがおはぎ??
桝の中にあんこがぎっしりですよ!?
これを見て、はた、と我に返りました。ブラマンジュとか頼んでる場合じゃないよ、私のあんこ者としての誇りはどこに行ってしまったの?
「…よかったら変えてあげようか?」
Yさんが、そんな私の気持ちを察してすっと助け船を出してくださいました。
「そうだよ、あんこ好きとか言ってブラマンジェたのんでるのは、むとうさんらしくないよ」
とSさん。そ、そ、そうだよねえ。私のバカバカバカ!!
そんなこんなで、やさしいYさんのお心遣いにより、無事、あんこ道の道から外れなくて済みました。…というわけで実食!
Yさん、ありがとうございます~!
 ぎっしりみっちり桝の中にあんこともち米が入っています。
ぎっしりみっちり桝の中にあんこともち米が入っています。
あんこは…わああ、おいしい!この小豆すごい!すごくボトムが強いというか、かなりコクの強い味。でもすっきりとしてるんです。もたれない。
メニューをもう一度見ると、なるほど小豆もこだわりの逸品。北海道旭川産の「しゅまり小豆」なんだそうです。福居製餡所さんのあんこだそうですよ。うまひ・・・
そしてこのもち米のほうにも少し塩見があって、すごくいいコンビネーションです!
 掘り進めていくと、したのほうにもあんこが入ってますよ!嬉しいなあ!
掘り進めていくと、したのほうにもあんこが入ってますよ!嬉しいなあ!
一見重たく見えるかもしれませんが、すごくすっきりとしてるので、デザートとして全然ありです!
おなかは一杯だったはずなのに、ぺろりと平らげてしまいました。
渋谷に行ったら、絶対また食べにこよーっと。
d47 shokudo
http://www.hikarie8.com/d47shokudo/menu/2013/10/10.shtml

 すっかり日が落ちて真っ暗です。なので、光源は街頭の灯り。いい年して公道で立ち食いをするだけでなく、写真も撮ろうというこの魂胆。
すっかり日が落ちて真っ暗です。なので、光源は街頭の灯り。いい年して公道で立ち食いをするだけでなく、写真も撮ろうというこの魂胆。 あんこは、甘さ控えめでほっこり。何度食べても飽きない味です。ほんと、変わらない味ですよ。そこがいい。
あんこは、甘さ控えめでほっこり。何度食べても飽きない味です。ほんと、変わらない味ですよ。そこがいい。