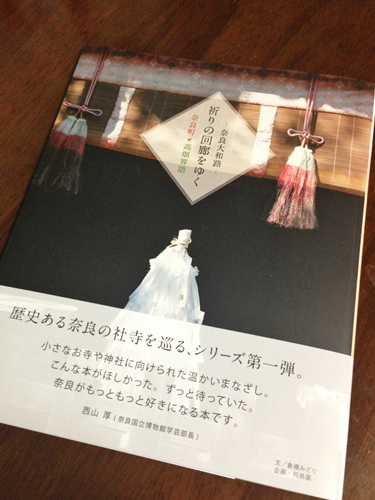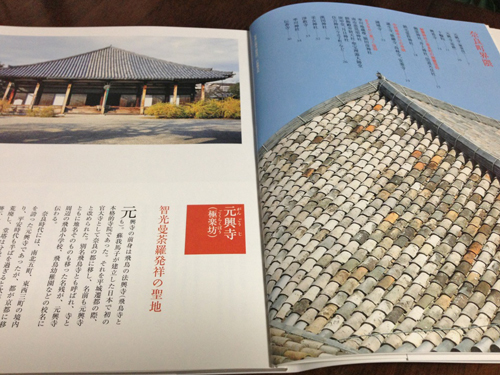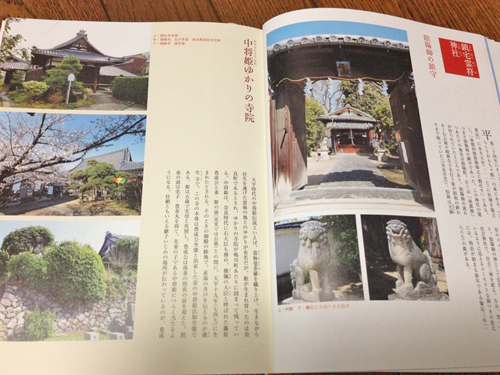いつもお世話になっているPHP文庫のN編集長から「仏像の本でたから進呈するよ~」といただいたのが本書。
タイトルと著者のお名前を見て「あれ?これはひょっとして…」と思ってまえがきを拝見したら、…やっぱりそうだ! 『壊れても仏像』という単行本を改題して文庫化したのが本書、とあります。そういうことだったんですね!
わあ、懐かしいな~。
 かつて働いていた出版社で、仏教美術ものをがっつりやらせていただいていた時に、『壊れても仏像』が出版されたのです。もちろんいそいそと購入いたしました。
かつて働いていた出版社で、仏教美術ものをがっつりやらせていただいていた時に、『壊れても仏像』が出版されたのです。もちろんいそいそと購入いたしました。
出版社を退職し、引越しをする際に手放してしまったので、思いがけずちょうだいしてとても嬉しい!
仏像を実際に修復されている方が、一般読者に向けて「仏像」について書かれる、というのは当時も今も、とても珍しいことですし、貴重です。
しかも、著者である飯泉さんは、当時まだ34歳とお若くて、その点でもとても珍しいことでした。内容も実はとても真面目なんですが、かなり砕けた表現をとられていて読みやすく、お人柄がしのばれる文章です。
ちなみに、余談ですが。
飯泉さんは独立される前、文化財の修復など行う美術院で長らくお勤めされておられたとプロフィールにあります。
……美術院さんか~。
これは全く私の個人的な思い出なのですが、美術院さんは何度かお写真を借りるなどのお願いで、お電話することがあったのですが、そのたびに応対してくださる方がみなさん丁寧・親切で、こころが洗われるような思いをしたものでした。
仏教美術にかかわらず、文化財掲載関係のお仕事してますと、たらいまわしにされたり、忘れられたり、ごくまれにですが関係のないことでお叱りを受けたり、…と、お電話して切ない気持ちになることもありましたが、美術院さんにお電話した中でそんな気持ちになったことはありません。
「こういう優しい方々が、仏像を修復してるんだな~、それはいいなあ~。正しいなあ~」
と一人頷きながら、悦に入ったものでした。飯泉さんもきっとそんな方なんじゃないかな、と勝手に想像してみたりして。
さて、僭越ですが、本書の特徴を私なりにご報告いたしますと。
やはり何より貴重なのは、仏像の基本的な知識はもちろんですが、仏像の修復がリアルタイムでどのようになされているか、というお話が掲載されていることです。こういったお話はなかなかうかがう機会はありません。
国指定の文化財なんかですと、まだそういうことを伺うチャンスはあるかもしれませんが、文化財になっていないもの、でも集落の皆さんが大切に守ってこられたお像についてなんかのお話は、なかなかうかがえないですよね。そんなお話もご披露されていたりして、とても面白いです。もちろん修理する当事者ならではのお話もこのご本ならではですね。
文庫化されるにあたって『仏像のお医者さん』というタイトルにされたのも、いいですよね!この新しいタイトルのイメージ通り、わかりやすく読めるように配慮された、「仏像そして修復」について書かれた貴重な一冊と思います。
仏像好きな皆さんには、特にお勧めです。もしまだ読んでいらっしゃらない方がいらしたら、ぜひ。文庫になってお手軽になりましたし!