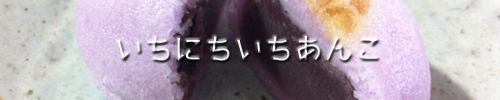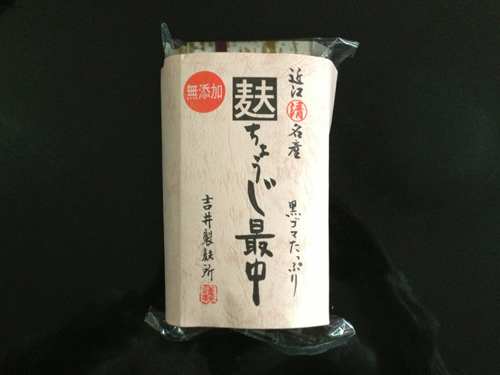先日の新潟旅がとても楽しい時間だったので、その後も新潟県民のかたがたのtwitterをちろちろ拝見しておりました。
すると新潟県民どうしのやり取りでちょっと気になった発言が…。
「新潟には何もない」
「関東にばかり意識が行ってしまう人が多い」
みたいなこと言い合っちゃってたんですけど、へえええ、と思いましたね。 何もない、新潟に??マジで??あんなにすごいところなのに??!…と思いましたよ。
関東の中で最も地味といわれちゃう埼玉県民としては、いろいろ共感部分は多いんです、そういいたくなる気持ちもわかります。
でも私は歴史から起こしてその土地を見る癖があるもんで、また見えてる風景が違うのかもしれない。 時代によって栄える場所というのは結構変遷があります。今栄えていても、100年前は狐が住むような薄野だったりするわけで、もちろんどちらが上、下という話ではありません。
例えば、7世紀くらいの日本地図で東日本を見ると、東日本で一番の都会は茨城県のあたりから群馬、埼玉北部中部、東京都北部あたりになるんじゃないでしょうか。 もっとひいてみると、6世紀初頭ぐらいの越の国(新潟は越の国のもっとも北に属します。ここでは広義の越の国という意味で)はある意味天下とってるし。越の国出身の継体帝とかね。
新潟って、その後も、上杉謙信とか、幕末の河井継之助とか、山本五十六とか、田中角栄とかいろんなすごい人がいますからね。すごいっすよ、ほんと。こないだ行ってつくづく思いましたが、歴史の重層的なところといい、江戸時代からそれ以降の豊かさによる文化の蓄積といい、はんぱないです。何もないって何の話ですか?みたいに思います。
 (写真はホテルから一望した新潟市内。ほかの国だったら首都ですわ。そもそもこの都市レベルすごいと思うけどなあ。)
(写真はホテルから一望した新潟市内。ほかの国だったら首都ですわ。そもそもこの都市レベルすごいと思うけどなあ。)
そういう話を聞くたびに思うのは、気づいてほしいなあ、面白がってほしいなあ、ということなのです。足元にある地面が実は見たままではないことを…。
新潟県民だけじゃないですよね。いろんな土地の人に言えると思うのです。
例えば、私が今住んでいる家(埼玉県中部)が建っているところは単なる住宅地ですけど、弥生時代からずーっと住宅地だったんですよ。何気にすごいと思うんです。見た感じではわかりませんけどね。まず、「人」の歴史という側面から見てもそんなふうにいえます。
そして、イキモノ的視野からもいろんなことが言えます。一見単なる土が広がる地面に見えても、そこに生えている「雑草」には実は美しいなまえがあるのです。そして無数の微生物や虫、さらには小さな哺乳類もいるのです。そしてもちろん大きな哺乳類・人が住んでいます。
またその土の組成もちょっと変わっているかもしれませんよ。地質学の人から見たら「お宝だ!」と騒ぐものかもしれません。地球史的に考えたらすごい何かがあるかもしれませんよ。
私は、そういうことに気付いていきたい、と思うのです。…小さいことですよ。とっても。 でも、そういうことに気付いていけるのって、すごい豊かだと、私は思っているのです。
「何もない」 という言葉があるとしたら、それは謙遜であってほしい。そう願ってやみません。